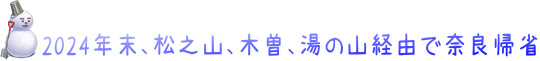 - その2 年末豪雪の魚沼エリアをうろうろ -  年末の関越道、関越トンネルを抜けるとしっかり豪雪でした。 |
|||||
(2024年12月24日-27日 その2) |
|||||
  |
|||||
なるほど、ここから先は雪ありということで全車両を赤城高原SAに導き入れてタイヤ確認というわけです。なお「チェーン装着確認」とは、スタッドレスタイヤ装着(またはノーマルタイヤ+チェーン装備あり)の確認ということのようで、これが「チェーン規制」になるとスタッドレスタイヤを履いていてもチェーンを装着しないと走れなくなります。 |
|||||
  ついでにちょっと休憩。この日最後に見たおひさまとともに。   |
|||||
山あいを進むにつれて路面にも雪が出てきまして、水上ICあたりからは雪道に。というわけで谷川岳PAに入って水汲みです。この谷川岳PAと新潟県側の各SA/PAには散水設備があり、駐車場に雪はありません。本州だからこの手が使えますが、より寒い北海道では大変だよなぁ。 |
|||||
  |
|||||
関越トンネルを抜けた先で、これまた全車両が土樽PAへと誘導されます。これもまた安全対策なのでしょう、トンネル内をハイスピードで走ってきた車がトンネルを出た瞬間に雪道に突入‥いやぁそれって怖すぎるし。 |
|||||
    |
|||||
というわけで雪の関越道を走っていきます。「新潟県へようこそ」の看板も雪を被っており、何だか「試されている感」があります。というのも本格的な雪道走行は久しぶりなのです。慎重にゆっくり進んだつもりですが、他の車に追いつかれたのは1台のみでした。かなり前方を行く車と同じ距離を保つように心がけ、塩沢石打のSAで休憩。 |
|||||
  |
|||||
ということで日帰り施設の湯らりあへ。こちらは朝9時から営業していますので、到着時(9:15ころ)はばっちり営業中、しかも先客の車は見当たりません。よしよしと思って入館してみると‥係員さんいわく、 |
|||||
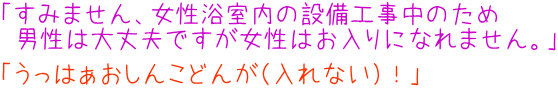 |
|||||
しかし心やさしきわが妻の「せっかく来たんだから入っていきなよ、わたしは待ってるから」という言葉に背中を押され(うそつけ入る気満々だったくせに)、いざ脱衣場へ。撮影禁止の掲示はなかったのですが‥ |
|||||
というわけで湯画像は諦めて静かに入浴いたしました。冷えた身体にしみ渡る湯は体感で44度ほどでしょうか、聞いていたとおり熱めの湯です。六日町温泉13号・15号の混合泉ということですから、源泉は先述のこぐりやま山荘と同じですが、源泉から近く熱いこともありピリ感あり。しかしまぁ浸かってしまえば湯ったり湯らりあ。 |
|||||
 |
|||||
なお上にも書いたように館内に撮影禁止の掲示はなかったと思いますが(必ず確認しているので)、ネット上には「撮影禁止になった」との情報もありますので、もしそうだとしたらゴメンナサイです。 |
|||||
なのだそうです。道路名に「快速」という単語が用いられているのは珍しい気がします。そのうち「○○特別快速特急道路」とかできませんかね(可能性なし)。それはともかく上沼道は全長60kmにもなる高規格道路ということですが、全線開通はいつになることやらです(いまだに未事業化区間があったりしますので)。 |
|||||
   |
|||||
いわゆる定食屋の「志なのや」さんに11時の開店と同時に入店。多くの定食以外に鰻の取り扱いもあり、また夜の部用の一品料理も豊富です。ご夫婦でのツーオペのようで、奥さんの接客が丁寧でした。しかし雰囲気だけで「高評価」が付くわけでもないでしょう。 |
|||||
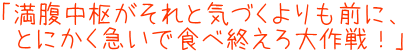 |
|||||
を発動しました(笑)。おかげでこの時ばかりはおしんこどんよりも早く食べ終わりました(普段は自分のほうが遅い)。よーし残さず全部食べたぞ!やればできるわけですが、普段それを回避しているのは「(1)満腹になるとてきめんに眠くなることが多い(運転危険)」のと「(2)食後しばらくすると個室トイレに急に行きたくなることが多い」からなのです。 |
|||||
もくじページのトップにトンネル画像を貼ったのでもうおわかりかと思いますが、われわれが目指したのは「清津峡渓谷トンネル」でありました。絵的に映えるということで近年有名になった場所ですね |
|||||
 ちなみにこの日の清津峡までの行程図です(笑)。 |
|||||
  |
|||||
さてしかし、R117からR353に入り十二峠方面に進んでいくと一気に雪が深くなりました。モリモリ降ってます。このあたりは新潟県内でも豪雪地帯ということですが確かに。またちょうど除雪の合間だったらしく路面にもそこそこ雪が積もっており、慎重なハンドルさばきでわだち部分をトレースしていきます(上画像は帰り道に撮影した、除雪作業後のものです)。何といっても、地元ナンバーの軽トラがわだちを外して山側の側溝にはまり動けなくなっていたくらいですから(JAFを呼んだようでした)。 |
|||||
  |
|||||
さて清津峡の駐車場に到着です。ここに来たのは2回目で、かつて存在した日帰り施設の「よーへり」に入浴したんだっけ(この時です)。今は秘湯提灯宿が1軒だけになってしまいましたね。 |
|||||
  |
|||||
というわけで、われわれも長靴に履き替えて歩き出しました。普通の靴だと雪に潜って濡れるからという理由からでしたが、この長靴は実に重宝しました。特に清津館前の道路は水たまりに雪がたまってシャーベット状になっており、そのため一見すると水たまりには見えず、普通の靴で来た皆さんはそのまま進んで急に「うわ何だこれ!」と、初っぱなから「靴の中びしょ濡れ&つめツメタイ」モードになっていたようでした。 |
|||||
  |
|||||
清津峡渓谷トンネル。かつては渓谷沿いに遊歩道が延びていましたが落石事故のため通行禁止になりました(その昔の登山ガイドブック地図にも通行禁止の記載があったことを覚えています)。しかし貴重な観光資源を生かすために掘られたのがこのトンネルというわけです。そのためトンネル内には3本の「横穴トンネル」があり、そこから渓谷美を鑑賞できるようになっています。まずは入ってすぐの事務所で入場券(1000円/人)を支払いますが、カードも使えるんですねびっくり。 |
|||||
  |
|||||
さて「横穴その1」にやってきました。当然見に行くと、眼下に渓流が見えるのですが(当然)、流れる水の表面には雪なのか氷なのかがたくさん浮いています。もしかしたら上流の斜面が雪崩れて大量の雪が沢に落ちたのかもしれません(違ったらゴメンナサイ)。 |
|||||
 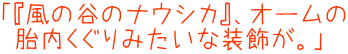 (何のこっちゃ)  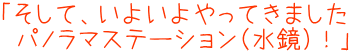 |
|||||
ここがトンネル終点なのですが、この場所には人為的に浅く水が溜められていて(1.5-2cm)、ええもうおわかりですね、水面に映る影とともに写真が撮れるフォトジェニックなポイントとなっているわけです。 したがって、普通ならトンネルの外に展望台を設けて云々なのに、ここを訪れる人はトンネルの中ばかりを眺めることになります(笑)。このアイデアって実にシンプルなのにありそうでなかったですよねぇ。 |
|||||
   (皆さんから歓声が上がる) |
|||||
ちなみにアジア系のグループは「一斉ジャンプ」などをしていたようですが、そうなると間違いなく足下はびしょ濡れになっていたでしょうね。われわれは長靴着用なので何の問題もありませんでした(ジャンプもしていませんし)。 |
|||||
  そうそう、見事な柱状節理。雪と岩とがいいコントラスト。   |
|||||
このあとは再び十日町市中心部まで戻り、なぜかワークマンプラスでお買い物。おしんこどんはウィンターブーツを購入し「ええ買い物したわ」とご満悦の様子でありました。 |
|||||
|