- その3 南会津、奥会津から六十里越経由で魚沼へ - |
|||||
 秋に戻ったり冬に進んだりとなかなか忙しい1日でした。福島県道349号にて。   |
|||||
(2024年11月22日-24日 その3) |
|||||
  |
|||||
R121は阿賀川の左岸を走っており西側には山が迫っていますから、あちらのルートだと虹は目にできなかったはず。たまたまのルート取りでしたが結果として正解でした。 |
|||||
  会津田島駅で小休止。蒸気機関車前のモミジはまだ秋の粧い。 |
|||||
ここからはR400を経由して舟鼻峠を越え、奥会津の会津川口へと進みます。この峠道って冬は結構雪深いイメージなんですがどうでしょうかね。ま、初めて通った頃は舟鼻峠も旧道による峠越えでしたから、今はずいぶん楽になりました。 |
|||||
  |
|||||
案の定、峠越えのトンネルを抜けて昭和村に入ると雪が舞っていました。積もる感じの雪ではありませんでしたがボタボタと落ちていました。というわけでもう少し進んだところで‥ |
|||||
  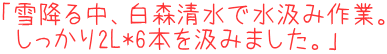 |
|||||
さらに下っていくと雪は止み、雨も収まったあたりで旧喰丸小学校へ。もうイチョウもすっかり葉を落としているだろうと思ってはいましたが‥ |
|||||
  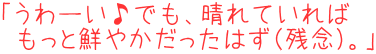   |
|||||
川口方面へさらに下って(標高を下げて)いくと、再び秋模様の気配が復活しました。何というか、当然のことですが「秋には色がある」のですよ。冬はモノトーンの世界ですからね。 |
|||||
  |
|||||
何でも八町の源泉は近年湯量が減っているそうで、源泉温度もあまり高くないことから向かいの玉梨源泉の力を借りているそうです。勢いよく投入されているのはおそらく玉梨源泉でしょう。 |
|||||
 |
|||||
八町温泉亀の湯は混浴なのですが、この時はちょうど先客の男女と入れ替わるタイミングでラッキーでした。玉梨の共同浴場ほど熱くはないのは浴槽の大きさと、また湯温41.8度の八町源泉も投入されているからでしょう。いずれにせよいいお湯をタンノーしました。 |
|||||
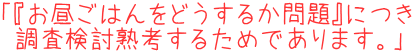 |
|||||
ここ金山町川口地区から只見方面へのR252沿いには飲食店が極端に少ないため、ここ会津川口で食べるか、一気に只見町の中心部まで移動してそこで食べるかというのが検討課題でありました。で、すでにお昼を回っていたため、「今から只見に移動していくうちに昼の営業が終了したら困る」というわけで「こちらで食べる」という結論に至りました。で、会津川口の食堂といえば‥「おふくろ」。こちらは‥ |
|||||
  |
|||||
一番上にトンカツが君臨し、その下には当然カレーが。カレーに覆われたその下には当然ラーメンがひかえているわけですが、それで終わりではなくどんぶり最底部にはどんとご飯が鎮座しているという、何だか、 |
|||||
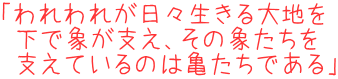 |
|||||
という、古代ヒンズー教に端を発した宇宙観をホーフツとさせるゴージャスメニューということであります(ただし簡潔に言えばその名の通りカツカレーとラーメンをミックスしただけなのかと)。 |
|||||
  |
|||||
未知の危機に対する回避本能が発動されました。ただあらためてグルメサイトを見てみると「量は思ったほどでもなかった」という感想もみられ、おしんこどんと一緒だったらチャレンジしてもいいかもしれないですね。いずれにせよ1人だと危険すぎたので(ちなみにTakemaはランチで牛丼屋に入るとミニ丼、ラーメン屋では半ラーメンを注文するヘタレです)。 |
|||||
 この第六只見川橋梁もトラス桁等が流出し架け替えられました。 |
|||||
その後このダムの補修につき貯水レベルを下げた結果「60年ぶりに現れた河原露天風呂」などの恩恵?もありましたが(その時のページはこちら)、その数ヶ月前に起きた東日本大震災と合わせて2011年は福島県にとっての「大厄年」だったのだなと今さらながらに思う次第です。それを考えれば浜通りも会津もよくここまで立ち直ってくれたなと。 |
|||||
 このあとは「会津のマッターホルン」との愛称を持つ蒲生岳を眺めた上で‥   |
|||||
只見駅へ。長らく運行を休止していた只見線の只見-会津川口区間も、再開通後2年以上になるのですね。ずっと以前に(2004/1)雪見鉄ということで乗ったことがあるのですが(そのときのページはこちら)、また乗りに来たいよなぁ(できれば平日に)。 |
|||||
であろうことが容易に想像できます。この日はここまで那須大丸温泉周辺やR400の舟鼻峠周辺で多少の降雪および雪道走行がありましたが、六十里越は越後と会津を隔てる脊梁山脈越えですから油断はなりません。もっとも、降雪で急遽通行止めになることを危惧していましたが、どうやらこの日の規制はない様子(安堵)。ここが通れなければ磐越道経由でぐるりと大回りするしかなかったので。 |
|||||
  |
|||||
只見川の流量逆調整池である只見ダムまではゆるやかな道が続きますが、右上画像のように「ご本尊」たる田子倉ダムの直下近くまで来たところでR252は一気に山道となり上り始めます。そりゃそうだ、田子倉ダムの堤頂部まで上がらなければなりませんからね。バイクでも車でも何度も通ってきた道ですが、特にバイクの時は遠く感じたよなぁ(古くはこの時とか)。いや実際千葉からは遠いんですが(笑)。 |
|||||
  |
|||||
というわけで田子倉ダムへ。人っ子一人、車も一台もおりません(閑散の極み)。幸いなことに雨は止んでいましたが、吹き抜ける風は冷たく、降り出したら雨になるか雪になるか微妙な気温です(たぶん雨かな)。 |
|||||
  そして、予想通り雪が舞いだしたと思ったら‥   |
|||||
六十里越トンネルの手前では何箇所か工事のため片側交互通行になっていました。この峠越え区間の冬季通行止めは2024/12/2からとなっていましたが、この前年(2023)は11/13からだったんです。2024の閉鎖時期が遅かったのは、左上画像のような道路補修工事が長引いていたからなのでしょう。この日は11/23でしたから「今年は通れてラッキー」という感じです。 |
|||||
   |
|||||
下るつれて雪は雨に変わり、再び「冬から秋へ」と逆戻りしました。このあとは道の駅ゆのたにで小休止後、なぜか「ワークマン魚沼店」で室内履きもこもこスリッパを購入し、さて六日町のお宿へと向かいます! |
|||||
|